「小論文の書き方が分からない」
「問題文を読んでもどう書き始めたら良いかわからない」
公務員試験における小論文試験でこのように悩まれたり、思ったりする方も多いと思います。コツさえ押さえれば「合格しやすい小論文」は誰でも作れます。
それらのコツを、小論文を採点する側から見た視点と5年以上の添削歴を踏まえ、お伝えしていきます。
問題文に対して、どのように対処していけばよいのかについてですが、下記のようにされると本番でも慌てずに書けるかと思います。

①まずは問題文で何が聞かれているのかしっかり把握する
小論文は制限時間があるため「早く書かなきゃ」と思うあまり、この工程をおろそかにしてしまう人が多いです。
そのような人に限って、問題文で求められていることが解答できていなかったり、解答しなくても良いこと(解答しなくても良いことを書いた場合は減点にはなりませんが加点もされません)をたくさん書いてしまい、合格答案から遠ざかるケースが多いです。
どのように落とし穴にはまってしまうのか、以下具体例で見てみましょう。
例1 ~を踏まえ、本市が行うべき取り組みを述べよ。
OK ○○市が行うべき取り組みは、待機児童の解消である。
NG 自身の強みであるコミュニケーション能力を活かして、~に取り組みたい。
(主語が「私」になってしまっているためNG)
例1の場合は主語が「本市」であるため「市が」行う政策を書かないと点数はもらえません。
問題文を流し読みしてしまうと主語が「本市」になっていることに気付かずに、「私が」行うことを書いてしまう受験生が多いです。
初めからこけてしまうと挽回ができませんので、主語の確認は必ず行い、何を書かないといけないのかを冷静に把握しましょう。

②いきなり本文を書かない。メモが小論文の成功を決める。
本文を書く前に下記の通りメモ書きで、書きたいことのアウトラインを書きましょう。
いきなり本文を書き始めて、途中で自分が書いている小論文がおかしいことに気づいても、その時には修正不可能なことが多いです。
そのようなことを防ぐために2、3分程度使ってでも、書きたいことのアウトラインを書いて、頭の整理を付けてから書き始めましょう。
本番はどのテーマが出ても、練習で書いた時と同じように、下記のような構成で書く、と決めておきましょう。
「今後食品ロスを削減していくために我が国が取り組むべきことを述べなさい。」
メモの例
①導入
我が国の食品ロスは非常に多い。食品ロスは~という観点からも、削減していく必要がある。
②第一に
第一に、事業者への取組が必要である。
具体例:食品の納入期限の緩和、フードバンク
③第二に
第二に、消費者への取組も必要である。
具体例:てまえどり、過度な鮮度志向の抑制
④まとめ
このように、食品ロスを削減するためには、~取り組んでいくことが重要である。
③メモに基づいてあとは書き進める。

まとめ、に関しては文字数調整の役割が大きいため、まとめを書いていたら文字数がオーバーしてしまう場合はまとめを0にしても良いです。逆に、まとめ以外のところで文字数が足りなさそうであれば、同じことの繰り返しになってもいいので文字数のためにもまとめを多めに書きましょう。
④まとめ
①から③ができれば、本番でも臆することなく小論文が書けるかと思います。小論文の書き方や、構成面(序論、第一に、第二に、結論)が固まればそのまま本番の小論文試験でも充分通用するので、練習を通じて自分なりのルーティーンを確立させておきましょう。

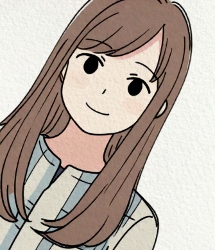
著者 元国家公務員mihir0
【経歴】
某旧帝大教育学部卒業後、地方公務員として市役所にて福祉関係の部署で勤務。その後国家公務員試験に合格し、総務課(局長の秘書業務)、人事担当の部署での勤務経験があります。地方・国家合わせて公務員歴は約10年。
現在は退職し、法律関係の仕事をしながら公務員試験プロ講師として稼働中。
公務員試験小論文・ES等の添削歴は5年以上、累計700件以上の販売実績があり、サービス利用者の方から、毎年多数の合格報告をいただいています。
[プロフィール詳細・顧客評価等はこちら↓]
https://coconala.com/users/653098
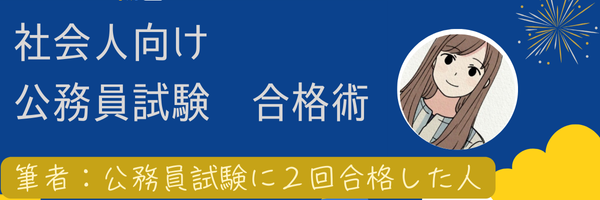
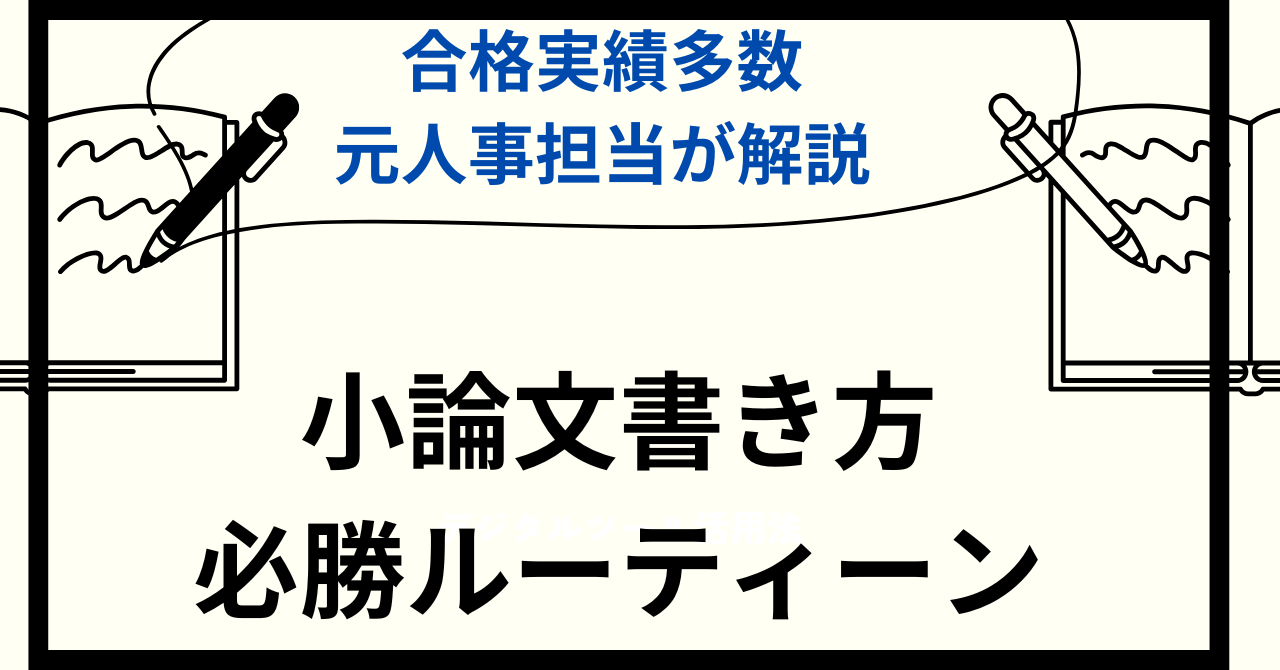
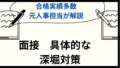
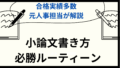
コメント