「市役所や県庁の面接対策って具体的に何をすれば良いの?」
「模擬面接を受けているのに結果が出ない」
と思っていませんか?
今回は、面接試験の本質を突いた、具体的な面接対策について、面接官目線から説明していきます。
筆者は独学で市役所に合格し、市役所での勤務経験があり、人事経験もあります。
筆者も独学時代にいろいろな対策をしましたが、その中には効果があったものや効果が無かったものもあります。
今回は筆者がやってみて効果があった対策、及び、人事経験よりこれはやったほうが合格率が上がる対策を紹介しますので、面接対策に活かして合格率アップにつなげましょう!

①公務員面接の実態
①-1面接カード命
面接合格のためには相手を知らなければいけませんので、まずは面接官のルーティーンを紹介します。
面接官は、あらかじめ受験者の面接カードをざっと見て、気になるワードに蛍光ペンを引き、そのキーワードについて深堀質問を考えます。
例えば川崎市のESで志望動機に「かわさきパラムーブメント」というワードが書いてあったとします。そうすると、そのワードに線を引いて、深堀質問を考えます。
質問例としては「かわさきパラムーブメントのどこに興味をもったのですか」「なぜ、かわさきパラムーブメントに興味をもったのですか」といった感じです。
面接前に、面接カードと履歴書を提出する自治体が多いと思いますが、履歴書は面接時の参考に見るだけであって履歴書から質問を考えることはあまりしません。
社会人の方であれば、職務経歴書(職務経歴書の提出が無い場合は履歴書)から質問を考えることは良くあるので、社会人の方は職務経歴書の書き方にも気を付けましょう。
①-2 非言語コミュニケーションも大事
面接における非言語コミュニケーションとは、清潔感、表情、姿勢、視線、声のトーン、身だしなみなど、言葉以外の要素を指します。
どれだけ話す内容が良かったとしても、これらの非言語コミュニケーションができていないと、面接官からの印象は悪くなってしまうので合格は難しいです。
とはいっても、最低限のことができればよいので、頑張りすぎる必要はありません。
たとえば、清潔感だとスーツのしわは伸ばしておく、髪の毛は整えて(女子だと後れ毛は出さない)顔に髪の毛が掛からないようにする、などがあります。
そんなことか、と思うかもしれませんが、筆者が人事経験で多数の受験者を見てきて、清潔感に欠けている受験生も少なくないので、他人事と思わずに自分事だと思って意識しましょう。
視線(アイコンタクト)については面接官の目をじっと見続ける必要はありません、
首元あたりや両目と鼻を結んだ三角形の中心に視線を固定すると自然な印象を与えられます。

②対策1 面接カード作成に力を入れる
②-1 自治体研究
面接ではその自治体をどれだけ知っているかを聞かれること(深堀されること)が多いので、自治体研究は必須です。
自治体研究をする際は、その自治体が出している「総合計画」を見ることが多いですが、「総合計画」は量も多く(200ページを超えることもあります)、すべて読むのは大変です。
そのため自分の志望動機や行きたい部署に関連する分野に絞って深く読むことをおススメします。
深堀されるときは、志望動機や行きたい部署に関連して深堀されることがほとんどなので、すべての分野に精通していなくても、志望動機や行きたい部署に関連する分野について詳しければ面接で十分対応できます。
例えば「子育て政策」の分野であれば、「総合計画」の「子育て政策」のページや「教育・学校」のページを見たりするだけではなく、ネットで「○○市 子育て 政策」で検索してみることをおススメします。
「総合計画」には載っていない情報がヒットしたり、市民向けに分かりやすく子育て制度を説明しているページが出てきたりしますので、面接で深堀されたときのネタとして使いましょう。

②-2 言いたいことはすべて書かない
面接カードは枠が狭いので、志望動機などは言いたいことがすべて書けないケースが多いと思います。
ただ、例外的に枠が広い面接カードを用意している自治体もあります。
面接官としては、面接カードに言いたいことがすべて書かれていると、質問内容に困ってしまうケースがあります。
面接官は面接で受験者とコミュニケーションがしたいので、コミュニケーションをさせてあげる必要があります。
面接でのコミュニケーションとは、受験者が面接官からの質問に答え、話の続きを質問され、それに答え、の繰り返しを言います。
面接での会話のキャッチボールとなり、コミュニケーションとなります。
そのため、面接カードでは、あえて肝心なところ(留学したエピソードなら、なぜその国に留学しようと思ったのかなど目的)をぼかしたり、あえて書かないなど面接官が質問する余地を残してあげるのが賢明です。
面接官が質問する余地が全くない面接カードだと、面接官も質問をひねり出すことになるので、変な質問ばかりされる可能性が高くなってしまいます。
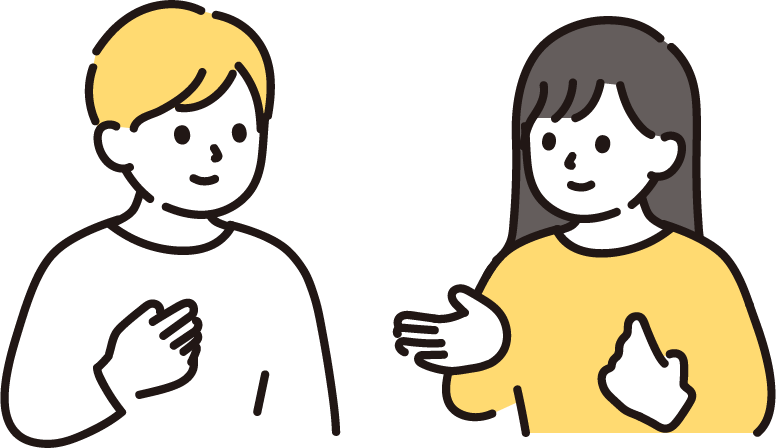
③対策2 模擬面接の活用
③-1闇雲に模擬面接を受けない
模擬面接はやみくもに数をこなしさえすれば良いものではありません。
適度に受けることが大切です。
皆さんは、会社の上司や同僚など、ビジネスで人としゃべるときに事前に練習をすることはないと思います。
模擬面接とは所詮、話し方や声の大きさ、しぐさなどの非言語コミュニケーションを整えるための手段に過ぎません。
面接に自信のない方は模擬面接を受けまくるより、まずは、面接カード(エントリーシート)のクオリティを高めましょう。
また、筆記試験対策でも、過去問や模擬試験を解きっぱなし・受けっぱなしでは力がつかないのと同様に、模擬試験も振り返りや復習が必要です。
模擬面接を受けたら、当日中に聞かれた質問、自分の回答、面接官役からのフィードバックをメモしておきましょう。
③-2 「深堀り多めでお願いします」と注文
個別面接などでは、自分の回答に対して面接官から深掘りをされることが多くあります。
そのため、模擬面接をおこなう際には「深掘りを多めにしていただきたいです」と最初に伝えることをオススメします。
④エピソードを整理する
真の面接対策は何なのかといえば、面接試験で話す内容を事前にまとめることです。

具体的には、面接カード(エントリーシート)の内容を詰めた上で、それに対して想定される質間に対し、どう答えるのかをまとめた簡単な想定間答集を作ることです。
想定問題集(想定される質間集)には二種類あります。
一つ目は一般的に良く質問される質問集(志望動機など)で、もうひとつは深堀質問集です。
一般的に良く質問される質問集はネットで検索すると出てくるのでそちらを使って対策されると良いでしょう。
深堀質問は面接カード(エントリーシート)をもとに面接で質問されるので、深堀質問集は面接カードをもとに自分で作成することになります。
模擬面接で面接官から深堀されたポイントをまとめても良いですし、面接カードの内容を見て深堀ポイントを探してまとめても良いです。
良くある深堀ポイントは、志望動機、市の政策についてどれだけ知っているか、ガクチカ(社会人の方は仕事で身に着けたスキルなど)あたりが多いです。
面接カードはスペースが限られていることもあり、簡潔にしか書けないケースがほとんどです。
簡潔にしか書けないため、簡潔に書いた面接カードの中から面接官がキーワードを見つけて、それについて深堀してくる(具体的に教えてください、とか言われる)というイメージです。
それをイメージして深堀ポイントを探してまとめておきましょう。
⑤第三者の力を借りるのも有効
自分一人では、面接カード(エントリーシート)が上手く書けないという方は、プロによる面接カードやエントリーシートの添削を通じて、事前に土俵をしっかりと築くのが効果的です。
面接対策を進めるうちに、自分が作った想定質問(特に深堀質問)や想定解答が正しいのかどうか、など悩みのタネが続々と出てくる場合もあります。
もし悩んだら、精神的な面やタイパの面からも、悩み続けるより、合格実績のあるプロの力を借りることをおススメします。
特に、面接カードの出来不出来は、面接の合否に直結するため、面接カードだけでも、プロの添削を受けたほうが、合格に確実に近づきます。
下記プロフィール欄にあるURL先では、小論文やエントリーシートの添削を通じ合格可能性の高い答案作成を行っています。ぜひ検討してみてください。
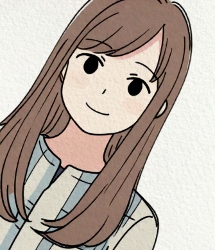
著者 元国家公務員mihir0
【経歴】
某旧帝大教育学部卒業後、地方公務員として市役所にて福祉関係の部署で勤務。その後国家公務員試験に合格し、総務課(局長の秘書業務)、人事担当の部署での勤務経験があります。地方・国家合わせて公務員歴は約10年。
現在は退職し、法律関係の仕事をしながら公務員試験プロ講師として稼働中。
公務員試験小論文・ES等の添削歴は5年以上、累計700件以上の販売実績があり、サービス利用者の方から、毎年多数の合格報告をいただいています。
[プロフィール詳細・顧客評価等はこちら↓]
https://coconala.com/users/653098
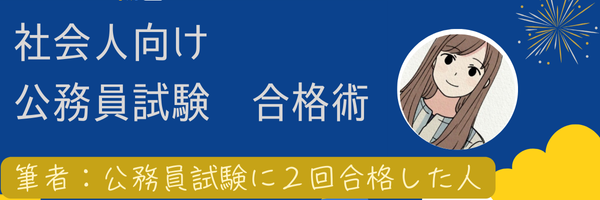
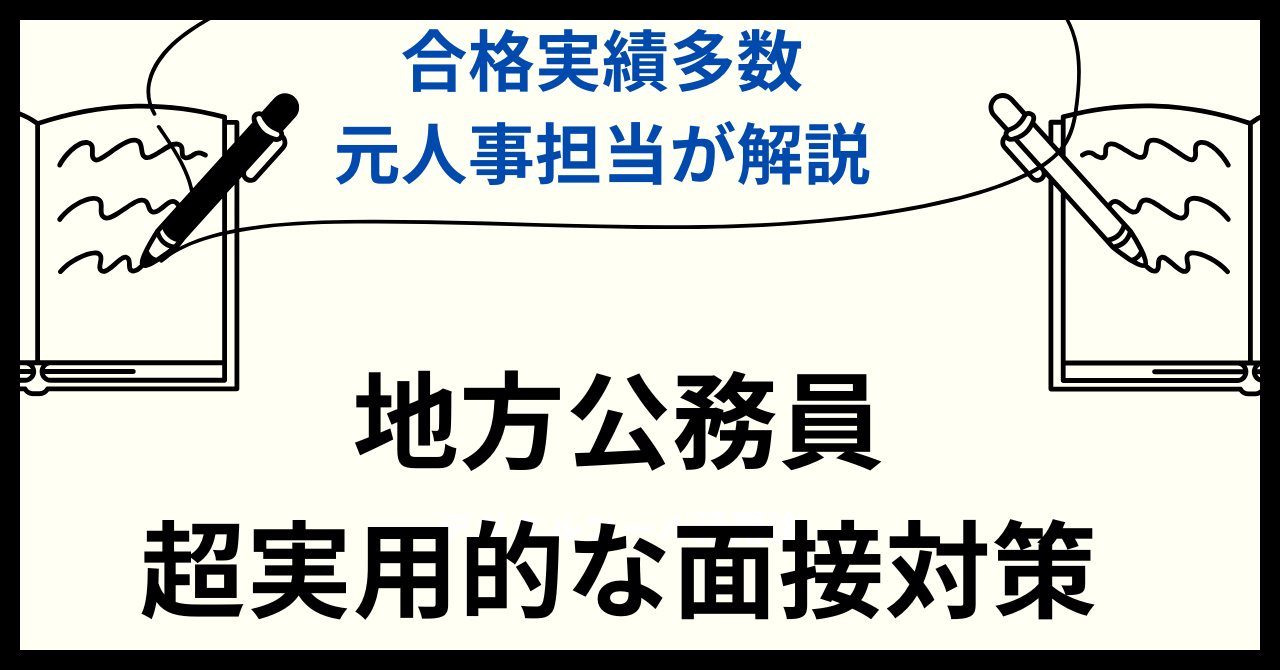
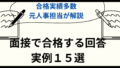
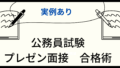
コメント