「小論文対策をしたいけど、試験要項に文字数の記載がない。」
「小論文試験の解答用紙って何割埋めればいいの?」
「足切りがあるって聞いたんだけど」
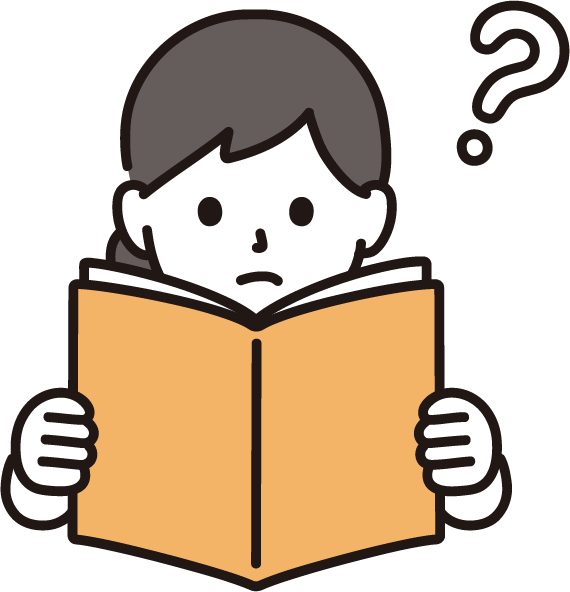
文字数は受験者にとっても採点する側にとっても重要チェック項目なので、公務員試験の受験先によってはこんな感想や疑問を抱く人も多いはず。
小論文の文字数について、事前に受験要項とかで案内があれば良いのですが、小論文試験について詳しい説明がないと、小論文試験の対策や練習がしにくくなってしまいます。「そんな状況でもなんとか本番で書くべき文字数を推測しよう!」ということで、今回は下記の通り小論文試験の試験時間を使います。
①試験本番の文字数はこれだ!
文字数の記載が無い場合でも、小論文試験の試験時間は記載されているケースは多いです。これまでの出題実績からして、下記のような比例関係となります。

(注)文量が多くても設問の要求に応えられていない場合は、基本的に加点されない。
自身の経験や、受験者の話をもとにすると、市役所や県庁だと1時間半の場合、文字数は1200字となるケースが多いです。
ほとんどの小論文試験は「○○字以内で述べよ。」と指示があるので、その文字数を超えてはいけないということになるので気を付けましょう。
たまに「○○字程度で述べよ。」という指示がありますが、その場合は多くても、その文字数の×1.1倍の文字数以内でおさめて書く必要があります。おそらく、解答用紙に書ける最大の文字数も「指定文字数×1.1倍」であるケースがほとんどですので、それ以上は書けないようになっています。
②文字数が少ないと採点対象外(足切り)となる可能性がある
「採点対象外」というのは、解答用紙に記入されているにも関わらず、採点されないので「0点」となってしまうことです。
自治体の受験案内では、小論文試験の点数が一定未満の場合は他の科目の点数が良くても不合格となる旨の記載があることもあり、これを一般的に「足切り」と言います。
具体的に説明すると、小論文試験の点数が低すぎると、他の科目の点数が良くて総合点で合格できそうであったとしても、落とされてしまうということです。
試験問題を作成する側からすると、問題に対して必要な回答を書いていれば大体この文字数になるだろう、と予測して制限文字数(「1200字以内で述べよ」など)を設定しています。逆に言うと、問題に対して必要な回答を書いていれば、指定文字数前後は書けるはずなので、あまりにも文字数が少ないと問題に対して必要な回答が書けていないと評価され、「採点対象外」となる可能性があります。
どの自治体も受験案内で「採点対象外」について、わざわざ述べてはいません。公務員予備校などでも上記のことが言われることが多いことと、小論文試験の点数が一定未満の場合は他の科目の点数が良くても不合格となる(いわゆる「足切り」)ことについては受験案内で明記している自治体もあることから、小論文試験において「採点対象外」が存在する可能性は高いかと思われます。
③解答用紙は最低8割は埋める。
制限文字数の8割以下だと絶対落ちるわけではありませんが、6割未満だと採点対象外となる可能性があります。採点対象外ということは、採点されないので「0点」と言うことです。問題に対して必要な回答を書いていれば8割以下になることはないので、6割未満だと問題に対して必要な回答が書けていないと評価されるからです。
この「必要な回答が書けていない」は大きな減点項目なので、具体的に何点減点かは、受験先によって異なります。ただ、公務員試験と言うのは他の受験生との競争試験なので、自分が大きな減点を受けてしまうと、大きな減点をしていない他の受験生に差を付けられてしまいます。
制限文字数の8割埋めていれば、文字数だけで大きく減点されることはまずありません。回答用紙全体の見た目も良くなるので、9割程度書けていると理想です。
今回は小論文試験の文字数にフォーカスしてお伝えしましたが、公務員試験を受ける方が悩みがちな、別のテーマでもブログを書いていますので、良かったらのぞいてみてください。
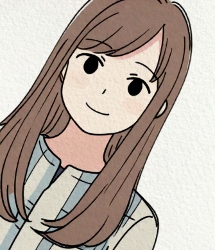
著者 元国家公務員mihir0
【経歴】
某旧帝大教育学部卒業後、地方公務員として市役所にて福祉関係の部署で勤務。その後国家公務員試験に合格し、総務課(局長の秘書業務)、人事担当の部署での勤務経験があります。地方・国家合わせて公務員歴は約10年。
現在は退職し、法律関係の仕事をしながら公務員試験プロ講師として稼働中。
公務員試験小論文・ES等の添削歴は5年以上、累計700件以上の販売実績があり、サービス利用者の方から、毎年多数の合格報告をいただいています。
[プロフィール詳細・顧客評価等はこちら↓]
https://coconala.com/users/653098
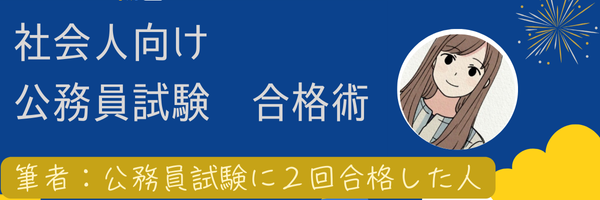
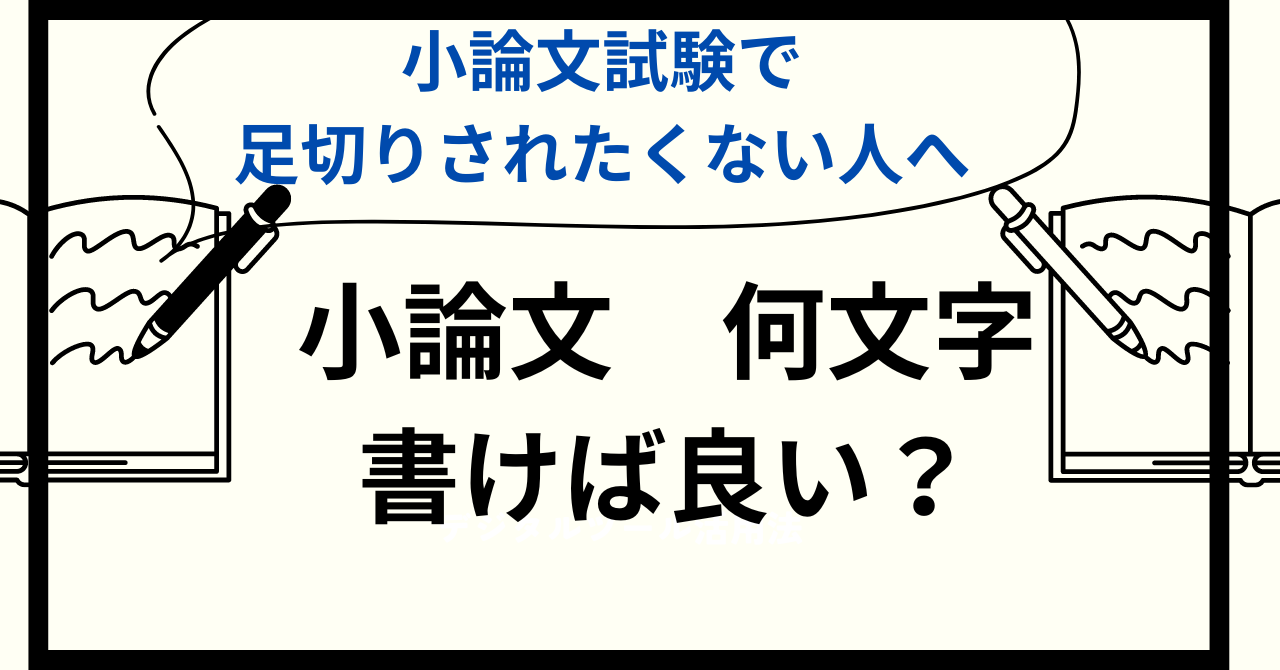
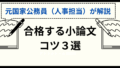
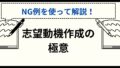
コメント