「面接で良くある質問や答え方が知りたい」
「面接での良い答え方、悪い答え方を知りたい」
という方のために、
今回は、面接官目線を把握している、元公務員(元人事担当)の筆者が、社会人採用試験における頻出の質問10個やそれに対応する模範解答例を説明していきます。

NG例も紹介していきますので、これを読めば、他の受験生がやりがちな失敗を避けながら、合格する面接回答作成が可能です。
ボリュームが多くなってしまったので、上から順番に読んでいただいても良いですし、目次をみていただいて気になる箇所のみ目次から飛んで読むこともできますので、適宜ご活用ください。
- 大前提として「話が長いと落ちる」
- ①頻出質問1 志望動機
- ②頻出質問2 希望する配属先とその理由を教えてください
- ③頻出質問3 希望する部署以外の部署に配属された場合はどうしますか?
- ④頻出質問4 後輩や部下の指導において、後輩や部下が自分より知識がある場合はどのように対応しますか?
- ⑤頻出質問5 ご自身の経験やスキルを○○市でどう活かせますか
- ⑥頻出質問6 上司と意見が対立したらどうしますか
- ⑦頻出質問7 県庁ではなくなぜ市役所を志望しますか?(市役所ではなくなぜ県庁を志望しますか?)
- ⑧頻出質問8 これまでの仕事で身に着けたスキルを教えてください
- ⑨頻出質問9 なぜ現職を辞めて公務員になろうと思ったのか
- ⑩頻出質問10 最後に、○○さんの方から質問はありますか?
- ⑪作った回答は第三者に見てもらおう
大前提として「話が長いと落ちる」
面接官から、「話が長い」と思われると、不合格となる可能性が格段に上がってしまいます。
人事で勤務していた時に、面接試験で、特に志望動機や自己PRを聞かれたときに一度にすべてを話す方が少なからずいらっしゃったのですが、話が長くなるので、面接官からの評価は低くなってしまう方が多かったです。

一度に話す時間が1分を超えると「話が長い」と思われるため、一度に話す時間は30秒から1分程度におさめておきましょう。
①頻出質問1 志望動機
OK例その1(営業事務)
これまでの業務にて、チームでの連携力を活かしてサービス品質を向上させてきた経験を活かし、人と時代に選ばれるまちづくりの実現に貢献したいと思い志望しました。前職では、メーカーの営業事務として、窓口対応を通じた顧客満足度の向上に貢献してきました。○○市に移住し、子どもとともに市の施設を利用したり、地域の方と接したりする中で住みよさを強く感じました。それを機に○○市について調べるうちに、児童クラブが日曜も開いているなど○○県内では○○市にしかない政策が充実していたり、大学や企業との連携が盛んであったりするなど、他の自治体に先駆けて新たなまちづくりに向けた取組をしている点に魅力を感じ志望しました。
OK例その2(不動産営業)
現職の○○業務において、人口が増加傾向にある市であっても既存住宅の活用が不十分であるために、住まいの課題や地域の課題に繋がっている市が多い現状を肌で感じました。これを機に、自治体職員として様々な施策を通じて住まいづくりを通じたまちづくりを推進したいと考えるようになりました。
○○市では○○の活用や○○など、新しいまちづくりの取り組みが行われている点に魅力を感じました。
これまでの、取引先との交渉の中で培ってきた調整力や対人折衝能力、不動産に関する知識を活かし、持続可能なまちづくりに貢献したいと思い志望しました。
NG例(地方公務員)
私は、○○県○市で生まれ育ちました。○○県は人口○○万人であり、都心部もありながら豊かな自然がある点も魅力的です。○○県で過ごす中で大自然や歴史・人柄に触れてゆくにつれて私にとって愛着ある場所となりました。私は大好きな○○県がその他県民の方々や海外の方々にもより一層住みよい場所にしたいという強い思いがあり、貴県職員を希望いたしました。
OK例のポイントは以下の3点です。
- ①ご自身の経験が含まれている
- ②受けたい市町村ならではの政策が盛り込まれている
- ③志望動機と①②がリンクしてい

NG例のポイント
- ①誰にでも言えそうな内容である
- ②内容が薄い
「生まれ育った〇〇市」は他の受験生も大体同じ出身地ですし、「生まれ育った〇〇市」というのはそれ単体では志望動機とは言えません。
面接官からしても、「生まれ育った〇〇市」単体で志望動機にしてくる受験者を何人も見てきており、正直見飽きている面接官も少なくありません。
そのため、避けたほうが無難でしょう。
②頻出質問2 希望する配属先とその理由を教えてください
OK例
○○部で児童福祉に関する仕事がしたいです。具体的には既存の施設である、○○の効果的な活用や、不安を抱えがちな乳幼児の保護者への支援等に取り組みたいです。○○で働く中で沢山の親子を支援してきました。しかし、現職にて関われる家庭には限りがあります。そのため、自ら市政に関わる事でより多くの家庭をサポートしたいと考えています。
ご自身の現職の知識や経験が生かせそうな部署を選ぶと良いでしょう。

③頻出質問3 希望する部署以外の部署に配属された場合はどうしますか?
OK例
配属先がいつも希望通りにならないことは承知しています。様々な部署で働くことは勉強の場になり、多くのものを吸収できるチャンスだと考えています。どこに配属されても、前向きに仕事に取り組みます。
④頻出質問4 後輩や部下の指導において、後輩や部下が自分より知識がある場合はどのように対応しますか?
OK例
自分より知識や経験を持つ相手に対しても、私は前向きに受け止めます。
現職でも中途入社の立場で、若手の先輩社員の専門知識に現場で助けられる場面が何度もありました。そうした際は素直に学び、私はサポート役に回るよう心がけています。
また、指導というよりも対話を重視し、相互理解を深めながら改善点を共有するよう努めています。ただし、コンプライアンスに抵触する場合は例外として、必要な指導を行います。
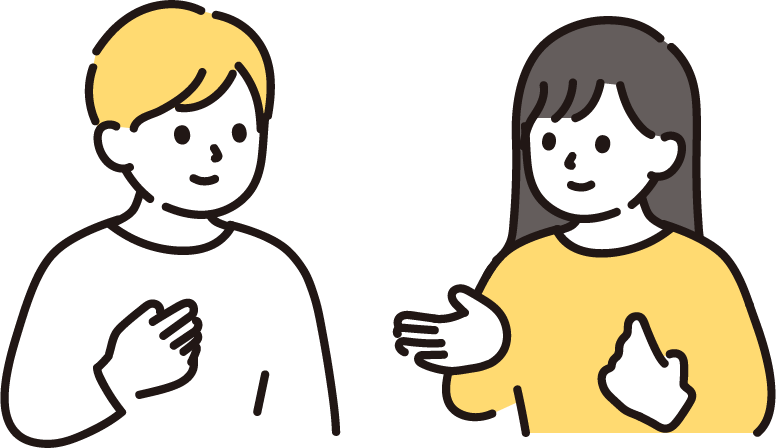
⑤頻出質問5 ご自身の経験やスキルを○○市でどう活かせますか
OK例
自身の強みである接客力とお客様の声をサービス向上に変える力は、特に福祉関係の窓口業務や審査業務等で活かすことができると考えます。窓口業務や審査業務を通じて市民の要望や、行政サービスの利用のしやすさなどを把握し、「真に利用者目線に立ったものか」という視点を持って市民サービスの向上に繋げることで、まちづくりに対する市民満足度向上に貢献することができます。
⑥頻出質問6 上司と意見が対立したらどうしますか
OK例
まず上司の主張をしっかりと聞き、上司の思考やその言動に至った背景も理解するように努めます。そのうえで、その指示に従っていくと現場で新た課題が発生してしまうといった懸念事項がある場合は、その考えをお伝えし、最終的な上司の判断に従うようにします。
NG例
組織の一員として上司の意見に従います。
OK例もNG例も「最終的には上司の判断に従う」のは同じですが、そこに至るまでの過程が大切なので、その過程が伝わるような答え方をする必要があります。

⑦頻出質問7 県庁ではなくなぜ市役所を志望しますか?(市役所ではなくなぜ県庁を志望しますか?)
OK例(県庁)
県職員は、多くの企業の方々や事業所と連携することができ事業として規模的に大きく取り組める点が強みであり、自身のスキルである連携力をより活かせるためです。例えば、障害者の一般就労支援に対して多様な就業環境を作っていく為には、県職員であれば専門員の方と連携することが可能になり、連携しながら広域的に県内各地、求職者と企業をマッチングしていくような場を形成できると思います。このような取組は単独の市町村職員や民間企業、社会福祉法人の職員で対応することは困難ですが、県職員として対応可能であると考えます。
OK例(市役所)
県庁よりも市役所のほうが窓口業務が多く市民の方との距離が近いので、自身の強みである接客力とお客様の声をサービス向上に変える力をより活かせると考えたためです。
⑧頻出質問8 これまでの仕事で身に着けたスキルを教えてください
OK例
これまでの仕事で、円滑なコミュニケーション能力を身に付けました。現職では、○○会社で営業事務として営業職員のサポートだけでなく、顧客対応も行ってきました。顧客対応については日頃から、丁寧なヒアリングを心がけています。問い合わせ時点ではご立腹だったお客様がこちらの案内後には感情が落ち着き、感謝の言葉を頂くこともあるなど、コミュニケーション能力には自信があります。

⑨頻出質問9 なぜ現職を辞めて公務員になろうと思ったのか
OK例
現職の○○で働く中で○○という課題を実感しました。しかし、現職にて関われる○○には限りがあります。そのため、自身の○○という知識やスキルを行政にて活かすことで○○という課題を解決し、より多くの人のサポートに貢献出来ると考えたからです。
NG例
今までの経緯から、私は一つの職場で長期勤務できる正職員ということを軸に再就職を考えています。安定した雇用に魅力を感じ自分の望むキャリアを歩めると考えたことから志望しました。
福利厚生や雇用の安定を理由にすると合格からは遠ざかってしまいます。
OK例のようにこれまでの勤務経験と絡めると説得力のある回答ができます。

⑩頻出質問10 最後に、○○さんの方から質問はありますか?
OK例
○○市役所(県庁)で活躍されている職員さんの特徴を教えてください。
現職ではコミュニケーションを重視していますが、○○市役所(県庁)ではどのようなことを重視されていますか。
NG例
質問は特にありません。
逆質問をされるということは面接時間が余っているか、順調に進んでいるということです。
そのため、「質問は特にありません。」と話を終わらせてしまうのは印象が悪いだけでなく、面接で会話のキャッチボールをする余地がなくなってしまうことになります。
そのため、良い質問が思い浮かばなかったとしても、何も聞かないよりはマシなので、何か一つ質問をひねり出して質問しましょう。
⑪作った回答は第三者に見てもらおう
面接用の回答を自分で作っただけだと、どうしても独りよがり的な回答になってしまったり、面接官に意味や熱意が伝わらないケースが多いです。
合格可能性を上げるためにも、家族や、第三者に見てもらうことをおススメします。 下記プロフィール欄URL先の添削サービスでは、プロによる添削だけでなく、その方に合った合格可能性アップのコツもお伝えしていますので是非ご検討ください。
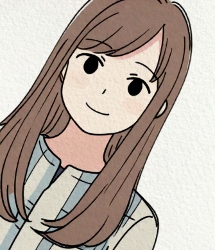
著者 元国家公務員mihir0
【経歴】
某旧帝大教育学部卒業後、地方公務員として市役所にて福祉関係の部署で勤務。その後国家公務員試験に合格し、総務課(局長の秘書業務)、人事担当の部署での勤務経験があります。地方・国家合わせて公務員歴は約10年。
現在は退職し、法律関係の仕事をしながら公務員試験プロ講師として稼働中。
公務員試験小論文・ES等の添削歴は5年以上、累計700件以上の販売実績があり、サービス利用者の方から、毎年多数の合格報告をいただいています。
[プロフィール詳細・顧客評価等はこちら↓]
https://coconala.com/users/653098
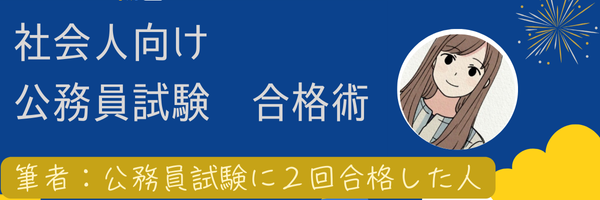
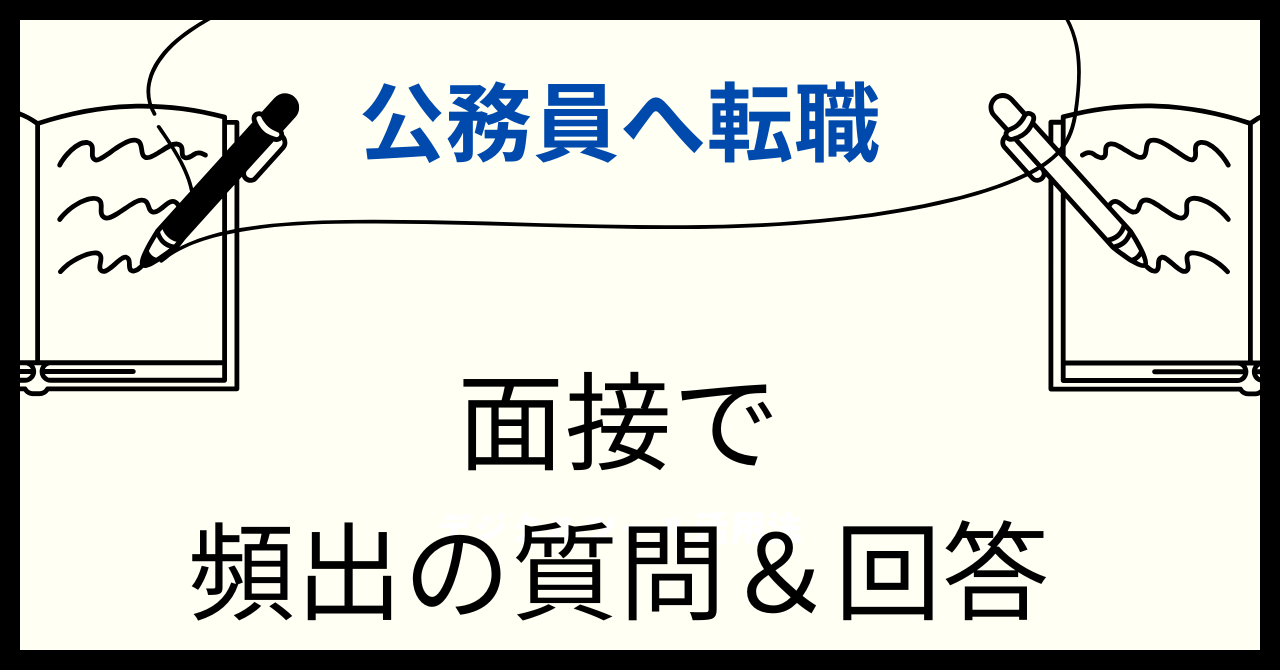
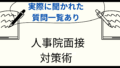
コメント