【小論文の答案作成方法】
「小論文の書き方が分からない」
「合格する小論文が書きたい」
公務員試験における小論文試験でこのように悩まれたり、思ったりする方も多いと思います。コツさえ押さえれば「合格しやすい小論文」は誰でも作れます。
それらのコツを、小論文を採点する側から見た視点と、5年以上累計800件以上の小論文の添削歴を持つ筆者がお伝えします。

【体裁(見た目)のチェックポイント3選】
何事も第一印象が大切です。いくら内容が良くても、体裁(見た目)が整っていないと、内容が評価されにくく、「合格しにくい小論文」となってしまいます。
公務員試験は「就職試験」です。択一試験は学力を客観的に見るものですが、論文は受験者の人物を評価するものなので、仮に同じ内容が記述されていても、評価に差が出てきてしまいます。
今回は、体裁(見た目)のレベルを上げる代表的なコツを3つお伝えしていきます。
(内容面のコツについては後日ブログにアップする予定です)
①「読める字」で書くこと
いわゆる「美しい字」である必要はありません。しかし、「汚い字」となると面接官に読んでもらえないか、読んでもらえたとしても深く読んでくれません。
本番は緊張&時間制限のため、多少の走り書きはやむを得ませんが、最低限「読める字」にはしておきましょう。
「とめ・はね・はらい」を意識したり、全体の文字の大きさを揃えるなど、は行っておきましょう。字に自信が無くても、これださえしておけば、全然「読める字」になります。
また、「汚い字になりやすくなる習慣」として、例えば「普段の論文の勉強を毎回パソコンで行う→本番のみ手書き」という習慣が挙げられます。
このように、全く字を書かない生活を続けていると字が下手になったり、本番で制限時間内で書ききることができなくなるので、特に普段から字を書く機会が少ない人は気を付けるようにしてください。
実際に文字を書くことも受験勉強の一つと考え、毎回とは言いませんが、適度に書く練習をしておきましょう。
②段落分けは必ず行う
小論文添削サービスを5年ほどさせていただいていますが、添削前の答案で「段落分けが一切ない」小論文を見ることがあります。
段落分けとは、文の始まりを1マス下げて書き始め、次の段落(文のまとまり)に移るときは改行して、次の段落の文の始まりを1マス下げて書き始めることを言います。文で書くと難しく聞こえますが、実際にやってみると全然難しくありません。
.jpg)
今回の図は文字数が少ないので、段落分けによる読みやすさが分かりにくいですが、1200字の小論文になると読みやすさが圧倒的に違います。本番で内容的に上手く書けなくても、段落分けによって、見かけ倒し的に小論文試験通過できちゃうパターンもあるくらい大切です。
③文末表現は、「だ、である」で統一する。
小論文に限れば、文末は「だ、である」で揃えましょう。作文は「です、ます」でそろえたほうが無難です。
一番やってはいけないのは「だ、である」と「です、ます」の混合です。
自覚がなくても、一生懸命書いているうちに意識が逸れて、文によって、文末表現が「だ、である」であったり「です、ます」であったりするケースが多々あります。採点する側からすると真っ先に減点対象となるので、気を付けましょう。
今回は代表的な3選をお伝えしましたが、ココナラの添削サービスでは、その方に合った合格可能性アップのコツもお伝えしていますので是非ご検討ください。
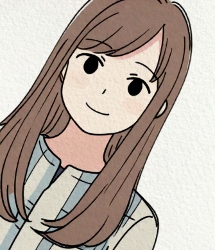
著者 元国家公務員mihir0
【経歴】
某旧帝大教育学部卒業後、地方公務員として市役所にて福祉関係の部署で勤務。その後国家公務員試験に合格し、総務課(局長の秘書業務)、人事担当の部署での勤務経験があります。地方・国家合わせて公務員歴は約10年。
現在は退職し、法律関係の仕事をしながら公務員試験プロ講師として稼働中。
公務員試験小論文・ES等の添削歴は5年以上、累計700件以上の販売実績があり、サービス利用者の方から、毎年多数の合格報告をいただいています。
[プロフィール詳細・顧客評価等はこちら↓]
https://coconala.com/users/653098
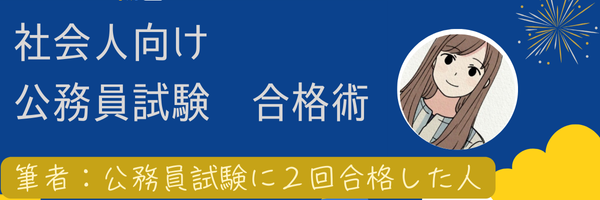
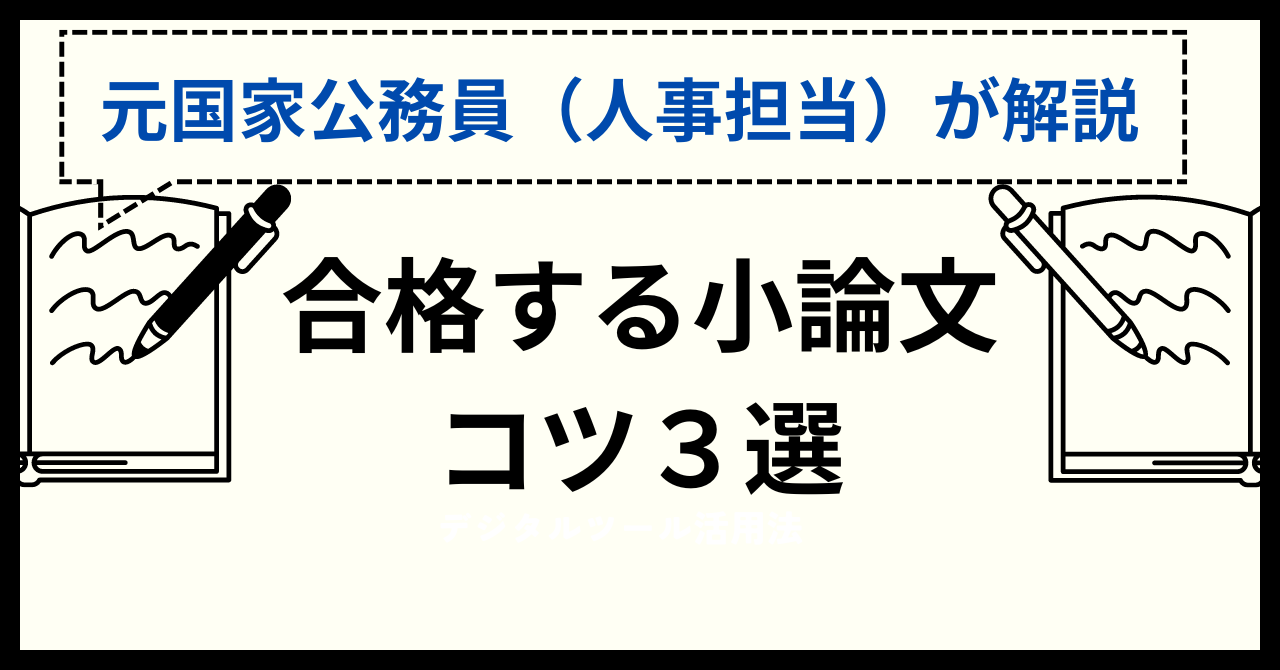
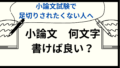
コメント
こんにちは、これはコメントです。
コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント」画面にアクセスしてください。
コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。